皆さん、こんにちは。長野県上田市を拠点に、県内全域で足場工事や仮設工事などを手掛けている株式会社ANZENです。
近年の建設業界は働き方改革が推進され、より安全かつ効率よく働ける環境が整ってきています。たとえば2024年4月からは、工事の安全性・作業性向上のため、いわゆる本足場の使用が原則として義務化されました。
https://www.anzen-support.jp/blog/column/166598
さらに建設業界では、さまざまな最新技術も導入され、働き方が大きく変わろうとしています。そこで今回は、建設業界に最新技術を導入すべき理由や、足場工事で活用される最新技術の具体例をご紹介します。
■建設業界に最新技術を導入すべき理由

これまでの建設業界は、他の業界に比べて最先端の技術の導入が遅い傾向がありました。しかし近年では、いろいろな理由により最新技術の導入が推進されています。主な理由は以下の2つです。
・人材不足の解消のため
人材不足は日本全体で問題になっていますが、建設業界では他の業界以上に人材不足が深刻化しています。主な原因は少子高齢化に加え、ハードな仕事内容のために人材の定着率が低いことや、そのイメージのために若い求職者から敬遠されやすいことなどです。
長時間労働の是正をはじめとする働き方改革は進んでいるものの、人材不足はそう簡単には解消しないでしょう。その対策として、少ない人数でも効率よく仕事ができるよう、最新技術の導入による効率化・生産性向上が求められているのです。
・安全性の向上のため
建設業は非常に労働災害が多い業界です。昔に比べると減少しているのですが、それでも他の業界に比べると多く、安全性の向上が長年の課題となっています。その対策となるのが最新技術です。最新技術によって作業員をなるべく現場から遠ざける、もしくは現場の危険性を低下させることができれば、安全性は大きく向上します。
このように最新技術の導入は、建設業界の働き方改革を実現する上で、もはや必要不可欠なものとなっています。以下の項目では、導入されている最新技術の実例を見ていきましょう。
■自動化技術で人材不足の解消に貢献

最新技術の導入と聞いて、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは、やはりロボットの活用ではないでしょうか。ロボットは人間の代わりに働いてくれるので、人材不足の解消に大きく貢献しています。足場工事においても、すでに以下のような形で活用されています。
・ロボットによる組立・解体
足場は多くの部材を組み合わせて作られる、とても複雑で巨大な設備です。しかし、人工知能を搭載したロボットは、すでに足場の組立・解体作業を自動で行えるところまで発展しています。決められた通りの作業をすることはロボットの得意分野だからです。
すでに一部の現場では、足場の組立装置が実際に使用されています。本格的に普及すれば、人材不足の解消や作業の効率アップに大きく貢献してくれるでしょう。
・自動搬送ロボット
足場の組立には大量の部材や工具を使うため、その運搬だけでも相当な労力がかかります。重い部材を落としてしまうなど、事故も少なくありません。そんな大変な作業をサポートしてくれるのが、自動搬送ロボットです。ロボットに材料や工具を自動で運搬させれば、作業員の負担が大きく軽減され、安全性も向上します。
■3Dモデリング技術で作業の正確性を高める
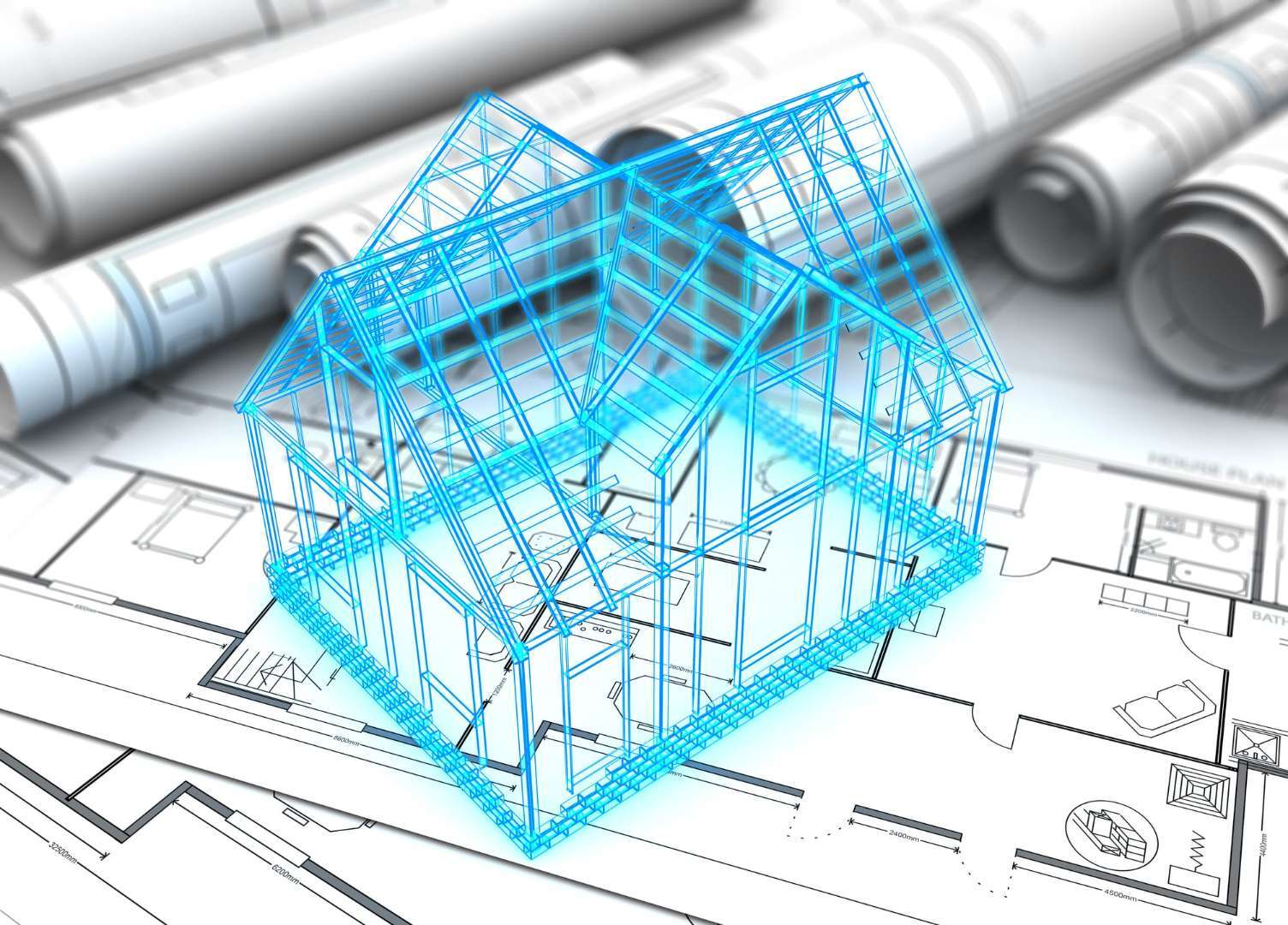
足場や建造物というものはとても複雑な構造をしており、完成時の姿を設計段階で正確に把握するのは、従来はとても困難でした。しかし現在では、3Dモデリング技術が実用化され、完成形を立体的に確認できるようになっています。足場工事における3Dモデルの活用法としては、以下のようなものが挙げられます。
・事前シミュレーション
3Dモデルの大きなメリットは、実際の足場の状態を事前に確認し、工事のシミュレーションができることです。シミュレーションの結果をもとに、より安全で効率的な施工計画を立てることもできますし、設計そのものを見直すこともできます。また、施主や関係者への説明がしやすくなるというメリットもあります。
・VR・ARを活用した作業支援
VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった技術も、作業支援に活用されています。たとえば、VR技術を使うと、3Dで構成された仮想空間の中で、実際の工事現場を体験・シミュレーションすることが可能です。事前に足場の構造や作業手順を詳しく把握すれば、作業の効率アップや安全性向上につながります。
また、作業員がARグラスを着用し、作業指示をリアルタイム表示したり、設計図やCADデータを表示して実際の現場と重ね合わせたりする技術も実用化されています。こちらもやはり、作業の正確性や安全性を大きく高めてくれる革新的な技術です。
■IoT技術の導入でより安全な作業現場を確保

IoT(モノのインターネット)技術も、建設現場に大きな革新をもたらしました。あらゆるものがネットワークで接続されることで、さまざまなメリットが得られるのです。特に安全面への影響は大きく、以下のような形で活用されています。
・センサーによる状態監視
足場は十分な強度を持っていますが、それでも何かしらのトラブルが起きたり不備があったりして、突然崩壊する可能性は0ではありません。それを防ぐために活用されているのが、センサーによる状態監視です。
このシステムは、ネットワークに接続されたセンサーが足場の状態を常にモニタリングし、傾斜や振動といった異常を検知すると警告を発します。これにより、足場の異常に早期に気づくことができ、事故のリスクを大幅に低減できるのです。
・遠隔監視
スマートフォンやタブレットを用いた、足場の遠隔監視も可能です。現場の状況をリアルタイムで確認しておけば、何か異常が生じても迅速に対応し、作業員の安全を確保することができます。
さらに、これらのシステムをクラウドと連携させれば、リアルタイムに収集された監視データを簡単に保存し、分析することが可能です。たとえば、足場の耐久性や劣化状況を把握してメンテナンスのタイミングを図るとか、作業中に生じた問題点の改善策を次回の施工に反映させるとかいった使い方ができます。
■革新的な軽量化された足場材も!

ここまでは、主に足場の組立・解体に関する最新技術を見てきましたが、足場材自体ももちろん進化しています。代表的なものの1つが、アルミニウム合金製の足場です。
アルミ合金製の足場は、軽量でありながら高い強度を誇ります。つまり、扱いやすい上にとても頑丈なのです。アルミ合金製足場が普及した結果、足場の組立・解体作業は、とてもスピーディかつ安全に行えるようになりました。
また、ポリマー素材製の足場も開発されています。ポリマーは樹脂素材の一種で、耐久性や耐候性に優れています。こちらもアルミ合金と同様、従来の鉄製足場に比べて非常に扱いやすく、作業員の負担軽減につながっています。
そして忘れてはならないのが、リサイクル可能な材料でできた足場が増えていることです。もともと建設業は環境への負荷が大きく、その削減が長年の課題となってきました。リサイクル可能な足場の導入は、環境への配慮のために推奨され、持続可能な建設活動に貢献しています。
■最新技術の導入ハードルは高い?

ここまで見てきたように、最新技術の導入は建設現場の作業性・安全性を大きく高めてくれます。しかしながら、最新技術の導入のハードルは決して低くありません。主な理由としては以下の2つが挙げられます。
・初期投資の高さ
多くの場合、最新技術の導入には高額の初期投資が必要です。そのため、有効性がわかっていても、予算の都合で導入に踏み切れない場合があります。
・人材育成の難しさ
どのような最新技術も、使いこなせてこそ意味があります。つまり、単に最新技術を導入するだけでなく、それに対応できる人材を育成しなければなりません。その時間とコストが、企業や現場にとって負担となる場合があります。
こういった事情により、最新技術の普及は決してスムーズではないのが実情です。そして見方を変えると、最新技術を導入している会社は、それだけ現場の作業性や安全性を重視している会社だといえます。建設業界で就職するなら、最新技術の導入に積極的な会社を探してみるといいでしょう。
株式会社ANZENは長野県上田市を拠点に、県内全域で足場工事や仮設工事などを手掛けています。現在、一緒に働いてくれる方を募集しております。
ANZENは創業以来、安全第一の理念のもと、高品質な足場工事を提供してきた会社です。本記事でも解説したように、2024年4月からは労働安全衛生法の改正により、高さ1m以上の高所作業においても本足場の使用が義務化されました。弊社ではこの改正を機に、さらなる安全性の向上に向けて取り組みを強化しております。
また、ANZENでは安全意識の向上を図るため、社員一人ひとりの声を大切にしています。社員が現場で感じた課題や改善点を、積極的に意見として取り入れることで、より安全な職場づくりを実現してきました。
もちろん、最新技術の導入にも力を入れています。皆さんも、安全に配慮された環境で足場工事のスキルを磨いてみませんか? 興味のある方はお気軽にご連絡ください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしております。
〉〉ANZENの採用情報
https://www.anzen-support.jp/service003
〉〉ANZENでの働き方
https://www.anzen-support.jp/work_style
〉〉ANZENのinstagram


